【実家じまい】何から始める?親が元気なうちに進める 後悔しない手順15完全ガイド:40代独身女性体験談
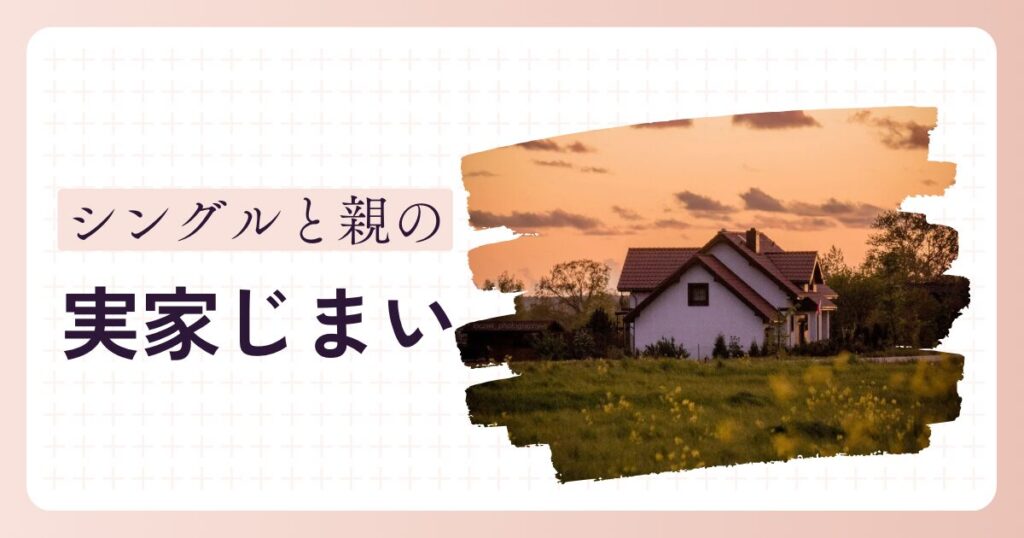
2025年2月更新
初めまして。40代シングル女性のあおこです。
このページでは「親が元気なうちに進める後悔しない実家じまいの手順」について、私の体験をもとにお伝えします。

私自身、2024年に親が元気なうちに実家じまいを終わらせ、
今は高齢の親と3人暮らしをしています。
私も初めて経験で分からないことだらけで、試行錯誤の連続でした。
多くの選択が必要な中で、途中ベストではない選択をしようとしてしまったこともありました。
しかし、その時々で色々な選択肢を考え、比較しながら計画的に行ったことで、結果的には後悔なく終えることができました。
中でも、親が元気なうちに実家じまいを終えたことは何より良い選択だったと考えています。
特に私と同じシングルの方は親御さんが他界されてから実家じまいをするとなると、負担が全てご自身にいく可能性が高いです。
また、親御さんの意向を確認できていない状態だと後悔されることも出てくるのではないでしょうか?
この記事を読むと、親が元気なうちに進める後悔しない実家じまいの手順がわかります。
シングルならではの視点や、実家じまい後の暮らしも考えた上でやったことなど、記載していきます。私の経験が、同じような状況の方の参考になれば幸いです。
・特に重要だと思った順に星
・シングルならではの視点を「シングルポイント」として記載しました。
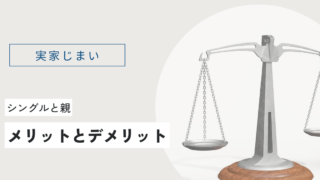
01. 準備:実家じまいをするか家族で相談

実家じまいを始める前に、まずは家族でじっくり話し合うことが最も重要です。
「実家をどうするか」を自分一人で決めるのではなく、家族全員が納得する形で進めることが後悔を減らす鍵となります。
特に親の意向やこれからの生活スタイルに大きく影響を与えるため、事前に十分に話し合い、みんなの意見を尊重しましょう。
実家じまいを行う際に考えたことは「この家はこれからの家族の人生にとって、どれだけ役に立つ場所だろうか?」ということです。
あおこ家では両親が高齢化しており、実家を維持メンテナンスすることの負担が大きくなっていることをきっかけに、家族全員で話し合い、実家じまいを決めました。
両親の気落ちだけではなく、私自身の気持ちも改めて整理しました。
考えたのは将来1人になった時に、どの様な生活をしたいと思っているのか?です。
あおこ家は田舎の一軒家で庭と畑もあり、1人で生活するには広すぎて持て余してしまうこと。車がなくても不便がない利便性の良いところに住みたい。と思っていることから、実家に戻ることは考えていないことを再確認しました。

焦らず少しずつ。
家族の未来にとって何が一番良い形なのかを相談していきましょう!


02. 準備:実家じまい後の生活設計を行う
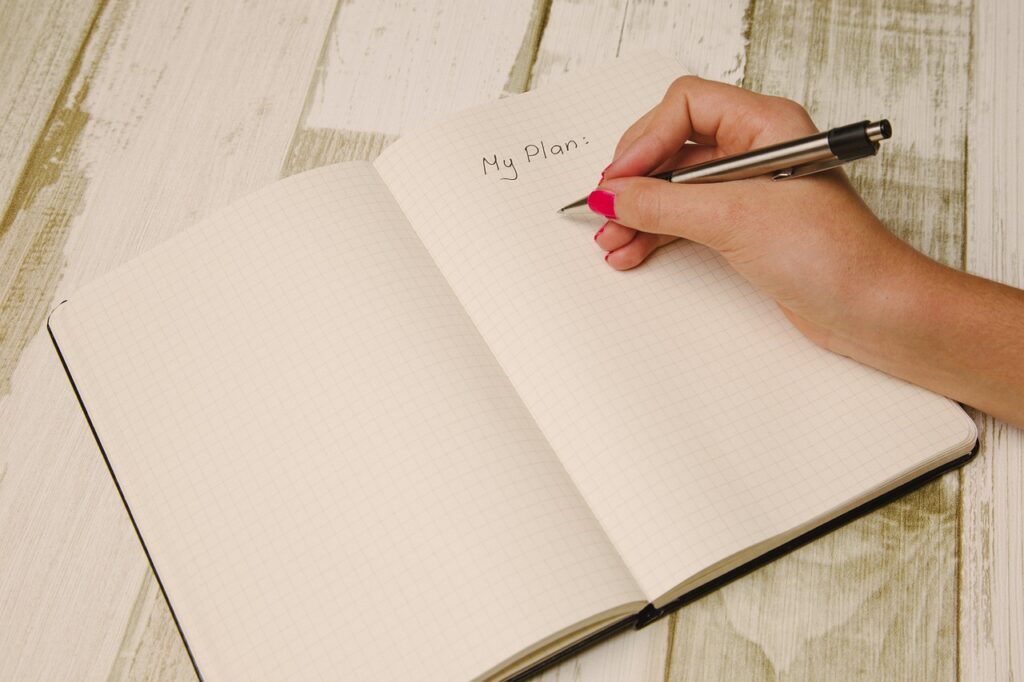
実家じまいをする決断をした後は、家族が今後どのように生活するかを具体的に設計しましょう。
特に親が高齢の場合、実家じまい後に必要となるサポートや生活環境を整えることが大切です。具体的には以下の様なことを考えました。
- 親が今後どの様な環境で生活したいか
生活する場所(同じ地域で暮らすか、別の地域で暮らすか)
生活の中で重視すること(個人空間を重視するか、複数人での生活でも良いか)
施設への入居をするか個人で住居を探すか - 親子で同居するか別居するか
- 定期的な通院をどうするか
- いつまでに新しい環境での生活を始めたいか
- 自分自身の将来の住居をどう考えるか
田舎の一軒家でしか生活したことがない両親にとって、同じ地域で暮らすか別の地域で暮らすのか。と将来を見据えて今から施設に入るのか。という判断がキーポイントになりました。
高齢者と一緒に暮らすための住居探しや引越し、住み始めてからの工夫は「シングルと親の生活」の方で今後記事にしていきます。
長い間1人暮らしをしており、自由な生活を楽しんでいたため、実家じまいをした
後の生活はとても悩みました。しかし、以下のことから同居を選択しました。
・両親が元気なうちに一緒の時間を過ごしたい
・将来介護が必要になった際にもできることをしたい
・両親は年金暮らしのため、収入の面で家を借りることにハードルがある
・一緒に暮らしてみて、どうしても無理だったらまた1人暮らしをすることを
前もって両親にも伝えておく

親の将来の介護も視野に入れ、
生活しやすい場所への引越しを決めました。

03. 準備:家の状態把握と市場相場を徹底調査

家を売る場合は、家の状態把握と市場相場の調査をしっかりと行いましょう。物件の価値を理解するために、複数の不動産業者に見積もりを出してもらうことが大切です。相場に合った価格設定を行い、売却後に必要な費用も事前に見積もっておきましょう。
家の状態によって、売る方法や売れる金額も変わります。家の築年数やメンテナンスの実績、家の中で壊れている箇所やそのまま使えない箇所がないか確認しましょう。
不動産屋と売買契約を行う際も、正確に家の状態を伝える必要があります。
また、市場相場を確認することは、相場よりも安すぎる価格で売ることを防ぎ、価格の目処がつけられることで、その後の生活設計もしやすくなります。
ただ、ここで得られる価格はあくまでも目安です。
具体的には以下のような方法で実家の売買価格の調査を行いました。
- 固定資産評価額を利用
- 公示地価・路線価で算出
- 近隣の物件の相場を調査
- インターネット上の査定サービスを利用
- 専門業者に相談
1. 固定資産税評価額を利用して算出:地価のみ
- 固定資産税評価額は、自治体が発行する「固定資産税の課税明細書」に記載されています。
「固定資産税評価額 ÷ 0.7」でおおよその目安を計算できます。
2. 公示地価・路線価で算出:地価のみ
- 公示地価は国土交通省が公表している土地の基準価格で、不動産情報ライブラリから調べられます。
- 路線価は国税庁が提供するもので、路線価格・評価倍率表から調べられます。
「路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積」
3. 近隣物件の相場を調査:地価・家屋両方
4. インターネット上の査定サービスを利用:地価・家屋両方
- インターネット上の査定サービスを利用すると、複数の不動産会社から査定結果を取得できます。これにより、相場感を把握しやすくなります。
5. 専門業者に相談:地価・家屋両方
- 地域密着型の不動産会社に直接相談することで、そのエリア特有の価格情報や売却戦略についてアドバイスが得られます。
これらの方法を活用し、ご自身で相場感を掴んだ上で、不動産会社に相談すると後悔なく納得感を持って進められるはずです。

私も不動産屋に相談する前にあらかじめ自分でも調べたことで、
ある程度予想をした上で相談することができました。
相場を確認し、家族で値下げされることも考慮のうえ、最低価格を相談しました。
04. 準備:家の処分方法を考える

実家じまいで家族で意見が別れやすいのが、家の処分方法です。家を売るのか、それとも貸すのか、解体して土地を売るのか、土地を別に活用するのか。これには家族全員の合意が必要です。
家の状態や場所によっては、リフォームをして売る方法もあります。自分たちの予算や希望をもとに最適な方法を選ぶことが、後悔を減らす第一歩となります。
「02. 準備:実家じまい後の生活設計を行う」で考えた将来設計を実現するにはどの方法が一番理想的なのかを家族で話し合いましょう。
具体的な家の処分方法は以下の様なものがあります。
- 土地・建物をのまま賃貸に出す
- 土地・建物をそのままで売る
- 土地を更地にして売る
- 土地を更地にしてさらに駐車場などで活用

当初は「土地・建物をそのまま賃貸に出し家賃収入を得る」「更地にして駐車場にして収入を得る」案などが出ました。
しかし、最終的には新しい場所での生活に集中したい思いが大きく、
売る際の手間が少なく、売った後のメンテナンスも不要である土地・建物そのままで売る形を選択しました。

05. 準備:売る時の優先順位を決める

家を売る際、優先順位を明確にすることが重要です。
「高く売りたいのか、早く売りたいのか」どちらを優先するかによって売却方法や価格が変わってきます。高く売ることを目指す場合は、家のリフォームや整備が必要な場合もあり、希望価格で買いたいという買い手が見つかるまでに時間がかかる場合が多いです。
早く売りたい場合は価格が低めに設定される場合もあります。
どちらを選ぶかは、家族の生活設計や状況により変わるのでよく考えましょう。
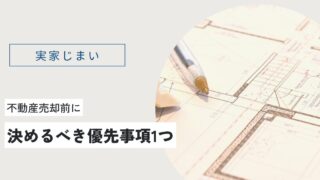

「早く売りたい」を優先させました。
高齢である両親の負担を減らし、できるだけ早く新しい環境での生活をスタートさせたかったためです。
06. 実践:信頼できる不動産屋を探す

実家じまいを進める上で、信頼できる不動産屋選びは非常に重要です。
「信頼できる良い不動産屋に巡り会えるかどうか」
と言っても過言ではありません。
良い不動産業者を選べば、家を高く売るためのアドバイスや適切な手続きをスムーズに進めることができます。一方で、不安な業者に依頼すると、不透明な契約や適正でない価格設定がされてしまう可能性もあります。
私が選んだ不動産業者は、実績が豊富で口コミでも評判が良かったため、安心して任せることができました。インターネットでのレビューや実際に他の方がどのような体験をしているかも調べて、信頼性の高い業者を選ぶことが大切です。
不動産屋の探し方には以下のようなものがあります。
- 一括見積もりサービスを利用
- ネットで個別に探す
- 知り合いの不動産屋に声をかける
- 不動産屋の店舗で直接相談する
実際に不動産屋を決定する際には以下の様なことを基準にしました。
・質問した内容に対して、明確で納得感のある回答が得られるか?
・経験値での話ではなく、事実をもとに数値で説明されるか?
・売り手の気持ちに寄り添い、誠意を持って対応してもらえるか?
・依頼する場合の今後の流れと役割分担が明確か?
・メリットだけではなく、デメリットも説明されるか?

複数の不動産屋に連絡し、価格や対応を比較しながら、
1ヶ月ほどかけて決定しました。
不動産屋には以下の様な内容を質問しました。
・売る価格の見積もりとその根拠
・仲介手数料
・売る際に、売り手の方で対応が必要な内容(境界確定など)
・税金
・売れるまでの期間の予想
・物件に対して考えられるデメリット、リスク
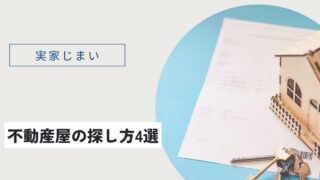
07. 実践:不動産媒介契約を結ぶ
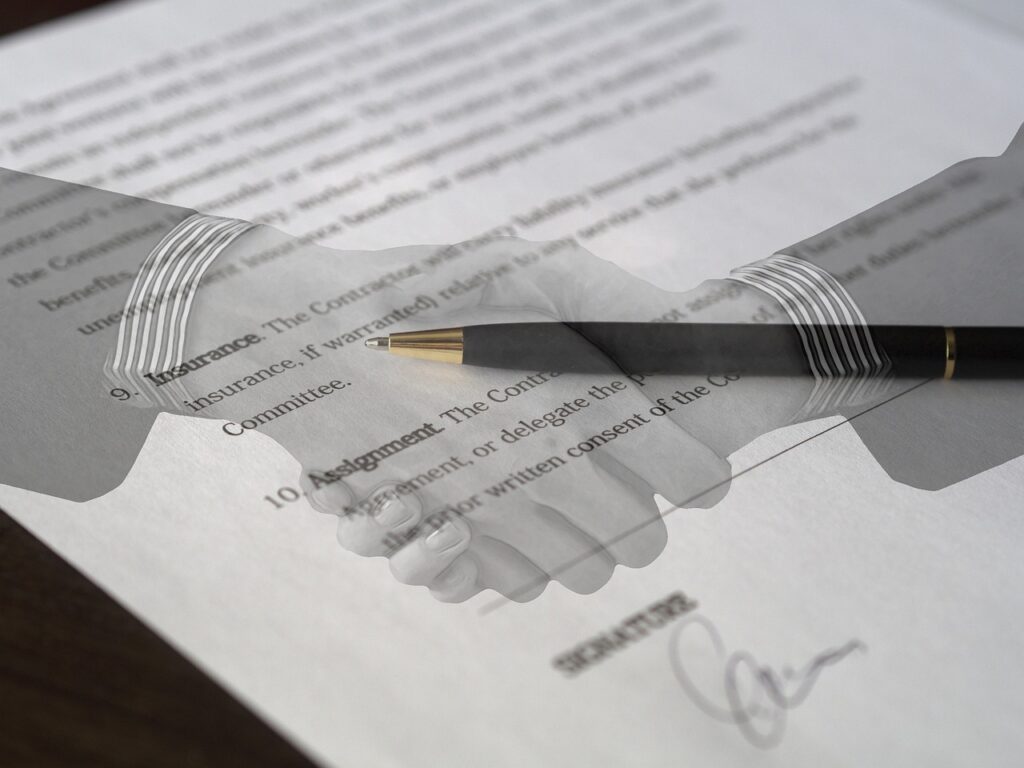
不動産屋が決まったら、次に行うのは「媒介契約」です。不動産屋と契約を交わし、どのように家を売り出すかを確認します。媒介契約には、主に「専属専任媒介契約」と「一般媒介契約」の2種類があります。
- 専属専任媒介契約
- 一般媒介契約
1.専属専任媒介契約
1つの不動産業者だけに売却を任せる契約です。業者は売却活動を積極的に行う義務がありますが、他の業者を使うことはできません。
2.一般媒介契約
複数の業者に売却を依頼できる契約です。柔軟に選択肢を持ちたい方に向いています。
柔軟な対応もできる反面、不動産屋から見ても優先度が下がる可能性が高いため、早さを優先したい場合は、専属専任媒介契約の方が良い場合が多いと考えられます。

「専属専任契約」を選びました。
1つの不動産屋に任せたことで、活動状況を確認しやすく、スムーズに進めることができました。
08. 実践:ご近所への連絡

家を売る際、ご近所への連絡を忘れないようにしましょう。実家が売却されることは周囲にも影響を与えます。事前にしっかり説明し、誤解を生まないように配慮することが大切です。
ご近所への連絡は、不用品処分の前に両親がご近所に日持ちのするお菓子を持って、ご挨拶に伺いました。
ご挨拶の際にお話した内容は以下の様なものです。
- 引越しをすることとおおまかな日程
- ◯◯という不動産屋に売却を任せることとしたこと
- 今後売却にあたり不動産屋から連絡させて頂くことがあるかもしれないこと
- 引越し等でご迷惑をおかけするかもしれないことへのお詫び
- 今まで長年お世話になったことの感謝

色々な業者が出入りする前に事前にお詫びとお礼を含めご連絡しました。
結果、ご近所の皆さんからのご理解も得られ、以降の手順もスムーズに進められました。
09. 実践:不用品を処分する

実家じまいの中で大きな作業の一つは、不用品の処分です。長年にわたって積み重なったものや、親が使わなくなった物を整理する必要があります。
家を売る際には、買手の方との調整内容にもよりますが、基本は家の中身は空っぽにしておく必要があります。
不用品処分のポイントは、引越しの日程から逆算し、大型で普段利用していないもの早いうちから計画的に処分していくことです。
また、不用品処分の方法も今は様々です。価値のあるものを売り、処分するものはゴミとして計画的に適切に捨てることです。
不用品処分の方法は以下の様なものを利用しました。
- 不用品回収業者に依頼
- リサイクルショップの活用
- 自治体の粗大ごみ回収サービス
- 解体して家庭ごみとして処分
- フリマアプリやネットオークションの利用
- 遺品整理業者の活用
1. 不用品回収業者に依頼
専門の不用品回収業者に依頼することで、大量の不用品を一度に処分できます。これらの業者は、リサイクル可能なものは買い取ってくれる場合もあり、処分費用を抑えられる可能性があります。
2. リサイクルショップの活用
まだ使える家具や家電、衣類などは、リサイクルショップで買い取ってもらうことができます。事前にクリーニングや簡単な修理をすることで、より高く売れる可能性があります。
3. 自治体の粗大ごみ回収サービス
費用を抑えたい場合は、自治体の粗大ごみ回収サービスを利用するのも良い選択肢です。ただし、事前に申し込みが必要で、回収日や対象品目に制限がある場合もあります。
4. 解体して家庭ごみとして処分
大型のものでも解体して規定の素材やサイズに当てはまれば、家庭ごみとして出すことで無料で処分できる場合があります。ただし、自治体のルールに従う必要があります。
5. フリマアプリやネットオークションの利用
まだ価値のあるものは、フリマアプリやネットオークションで売却することも検討しましょう。
6. 遺品整理業者の活用
大量の荷物がある場合や、感情的な負担を軽減したい場合は、遺品整理業者に依頼することも効果的です。これらの業者は、貴重品や思い出の品の仕分けも丁寧に行ってくれます。

実家じまいにおいて、良い不動産屋を探すことの次に大変だったのが不用品の処分でした。
一気に対応することは難しいので、計画的に進めましょう!

10. 実践:新居に引越し

次は新居への引越しです。実家じまいの場合、新居を決める際は両親の健康状態や生活スタイルをしっかり考慮しましょう。
また、引越しの際には、無理のないスケジュールで準備を進め、引越し業者も事前に見積もりを取り、比較することが大切です。
高齢の親と暮らすための物件を探したときのポイントやその後の生活については、「シングルと親の生活」の方でこれから記事にしていきます。
高齢の両親の引越しの負担をできるだけ減らすために、一人暮らしをしていた私が先に新居に引越し、生活環境を整えた上で両親に引越ししてもらうスケジュールにしました。

引越しは物件が売れてからにすることもできましたが、住んでいる状態で物件を見に来られることが高齢の両親の負担になると考え、売り出しの前に引越しすることにしました。
結果、両親にも喜んでもらえたので、可能な方は売り出しの前に引っ越すことを強くお勧めします。

11. 実践:価格を決定し物件を売出す

不動産業者と売り出し価格を調整・決定します。ここで決定して売り出した後は価格が上がることはないので、下がる可能性も考えた上で初期の価格を決定する必要があります。
価格が決まれば不動産業者の方で販売活動を行い、物件の写真や詳細をネットに掲載して宣伝します。
売り出しを行うと業者や物件が気になった方が物件を見に来たり、内覧を行ったりすることになります。
不動産の売り出し方は以下の様なものがあります。
- 不動産業界専用の物件紹介サイト(一般消費者は参照不可)
- 一般向け物件紹介サイト
- 不動産屋独自のつながりを利用
- チラシ・ポスティング
- 看板や旗の設置
12. 実践:買主と売買契約を締結する

買主が見つかり、価格等条件が整い相互に合意が得られたら売買契約を締結します。この段階では、法的な手続きをきちんと行うことが必要です。専門家(司法書士など)と一緒に契約書の内容を確認し、必要書類を準備しましょう。
契約書にサインする前に、すべての内容を細かく確認し、不安な点は質問して解決しておくことが大切です。特に不動産取引は金額が大きいので慎重に進めることが大切です。
売買契約は以下の流れで実施されます。
- 重要事項説明
- 売買契約書の確認と署名・捺印
- 手付金の支払い
- 必要書類の準備
- 物件状況等報告書・設備表の確認
- ローン特約(必要な場合)
1. 重要事項説明
- 売買契約の前に、宅地建物取引士が買主に対して「重要事項説明」を行います。
- 物件の権利関係、法令上の制限、設備の状況、管理状態(マンションの場合)などを詳細に説明し、書面を交付します。
- 買主はこの内容を確認し、不明点があれば質問することができます。
2. 売買契約書の確認と署名・捺印
- 売買契約書には以下の内容が記載されます
- 売買価格
- 支払い方法と期日
- 引渡し時期
- 契約解除条件(手付解除や違約金など)
- 物件の現状や設備の詳細
- 売主と買主双方が内容を確認した後、署名・捺印を行います。
3. 手付金の支払い
- 買主は売主に対して手付金を支払います。一般的には売買価格の5~10%程度で、現金で支払われることが多いです。
- 手付金は契約成立の証拠となり、売買代金の一部として充当されます。
4. 必要書類の準備
契約締結時には以下の書類や費用が必要です
- 売主側:
- 登記識別情報(または権利証)
- 印鑑証明書
- 実印
- 買主側:
- 身分証明書(運転免許証など)
- 実印
- 手付金
- 印紙代(契約書に貼付する収入印紙)
5. 物件状況等報告書・設備表の確認
- 売主は「物件状況等報告書」と「設備表」を提示し、物件や設備の状態、不具合などを明示します。
- 買主はこれらを確認し、納得した上で契約を進めます。
6. ローン特約(必要な場合)
- 買主が住宅ローンを利用する場合、「ローン特約」が付加されることがあります。
- 万が一ローン審査が通らなかった場合、手付金が返還され契約が無条件で解除される仕組みです。
以上の手続きを経て、不動産売買契約が正式に成立します。このプロセスでは、双方が条件に納得していることが重要です。不明点や疑問があれば、契約前に仲介業者や宅地建物取引士に相談することをおすすめします。

事前に書類をいただき、不明点は全て確認してした上で、
契約に臨みました。
初めての経験で後戻りできない契約は緊張しましたが、あらかじめ契約の際の流れと契約書の不明点を確認することで落ち着いて望めました。
13. 実践:追加で必要な情報を買主に提示する

売買契約後のこの情報提示や調整の段階で何かあれば、契約が進まなくなることもあるため、
正確に偽りなく情報を伝える必要があります。
物件によっては、境界の確定や土地の測量などの手続きが必要な場合があります。これを怠ると、後でトラブルになることもあるので注意が必要です。
買主に伝える情報には以下の様なものがあります
- 境界確定測量
- 物件状況確認書(告知書)
- 物件の価格に影響する事項の開示
- 売却理由の説明
1.境界確定測量
- 買主の多くは境界が確定している物件を売買の条件としていることが多いです。
- 境界線をめぐるトラブルを回避し、正確な売買価格の算出に役立ちます。
2.物件状況確認書(告知書)の作成
- 物件の瑕疵(欠陥)に関する情報を買主に提供する義務があります。
- 瑕疵には物理的、心理的、環境的、法律的なものが含まれます。
- 正確な情報提供を怠ると、買主から契約解除や損害賠償を請求される可能性があります。
3.物件の価格に影響する事項の開示
- 物件の価値や将来性に関わる重要な情報を買主に伝える必要があります。
- 例: 築年数、間取り、日当たり、管理費、修繕積立金、周辺環境など。
4.売却理由の説明
- 法的義務ではありませんが、買主の判断材料として重要です。
- ネガティブな理由の場合は、伝え方に配慮が必要です。
これらの対応は、円滑な取引と将来のトラブル防止に役立ちます。特に物件の瑕疵に関する情報は、必ず正確に伝える必要があります。
14. 実践:買主への最終引渡し

売買契約が結ばれ、物件が引き渡される最終段階です。
最終引渡しは以下の流れで実施されます。
- 残代金の受領
- 登記手続き
- 税品や費用の精算
- 鍵や書類の引渡し
- 引渡し完了確認
1. 残代金の受領
- 買主が売却代金の残金を支払い、売主がそれを受け取ります。
- 支払いは通常、銀行振込で行われます。
- 売主に住宅ローンが残っている場合は、この代金でローンを完済し、抵当権を抹消します。
2. 登記手続き
- 所有権移転登記が行われます。司法書士が手続きを代行するのが一般的です。
- 売主は「登記識別情報(または権利証)」や「印鑑証明書」を提出します。
- 買主は「登記費用」などを負担します。
- 売主に住宅ローンが残っている場合、抵当権抹消登記も同時に行います。
3. 税金や費用の清算
- 固定資産税や都市計画税など、不動産に関する税金を日割り計算し、売主と買主間で精算します。
- 管理費や修繕積立金(マンションの場合)も同様に清算されます。
4. 鍵や書類の引渡し
- 売主から買主へ以下のものを引き渡します:
- 鍵一式
- 測量図や境界確認書(戸建ての場合)
- 建築確認通知書や設備保証書
- マンションの場合は管理規約や使用細則など。
- 設備の使い方や注意点なども説明することがあります。
5. 引渡完了確認
- 鍵や書類の受け渡し後、「引渡完了確認証」に署名・押印を行い、引渡しが正式に完了します。
この一連の手続きを経て、不動産売買が完了します。
15. 実践:確定申告を行う
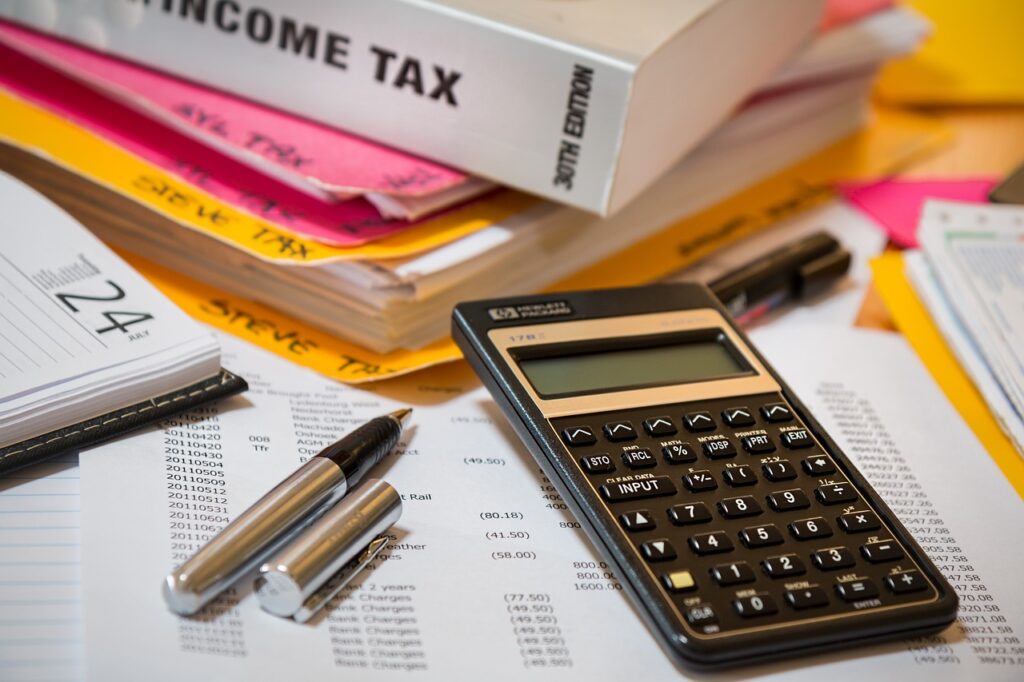
実家じまいで不動産を売却した翌年は確定申告を行う必要があります。
不動産を売却した翌年の確定申告の申告時期と方法は以下の手順になります。
申告時期
- 期間: 不動産を売却した翌年の 2月16日から3月15日 までが申告期間です。
申告方法
以下の方法で申告が可能です
- 税務署窓口での提出
最寄りの税務署に直接出向き、申告書を提出します。
ただし、申告期間中は混雑することが多いので注意が必要です。 - 郵送による提出
必要書類を郵送で税務署に送付します。
提出期限までに税務署に届くよう、余裕を持って送付しましょう。 - 電子申告(e-Tax)の利用
e-Taxでは24時間いつでも提出でき、還付金も通常より早く受け取れるメリットがあります。インターネットを利用して、自宅から電子申告が可能です。
e-Taxを利用するには、事前にマイナンバーカードや電子証明書、利用者識別番号の取得が必要です。
注意点
- 確定申告を期限内に行わないと、「無申告加算税」や「延滞税」が課される可能性があります。
- 所得税の還付申告の場合は、2月16日以前でも手続き可能です。
これらを踏まえ、必要な書類を準備し、早めに手続きを進めることをおすすめします。

依頼した不動産屋さん経由で税理士さんをご紹介いただき、税理士さんに手続きを実施しました。
過去に家をたてた時の費用やメンテナンス費用等を考慮の上計算する必要があり、少し複雑であったため費用はかかりましたが依頼して良かったと考えています。

高齢の親と3人暮らしを始めたシングル40代。
シングルと親の生活をできるだけ穏やかに
悔いなく過ごしたい。
自分の人生も楽しみ、更年期もポジティブに過ごしたい。
との思いから日々試行錯誤中。
私と同じようにシングルで親との生活や
自身の生活に悩む誰かの一例になれたら幸いです。
今のモットーは
「なんでも自分の気持ち次第!」



