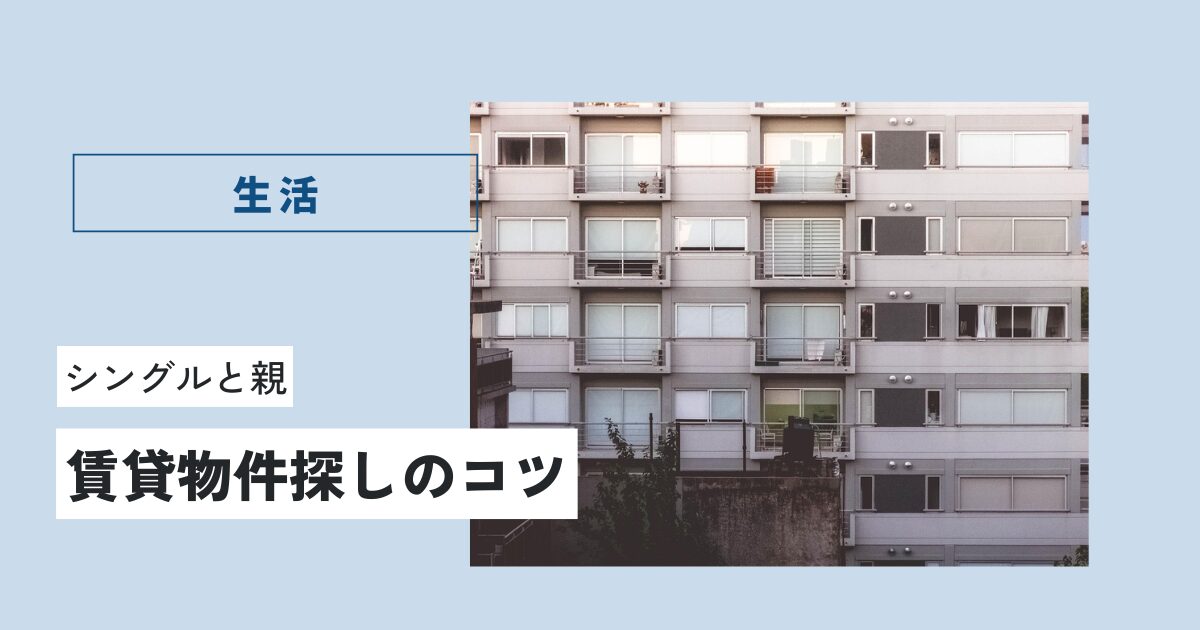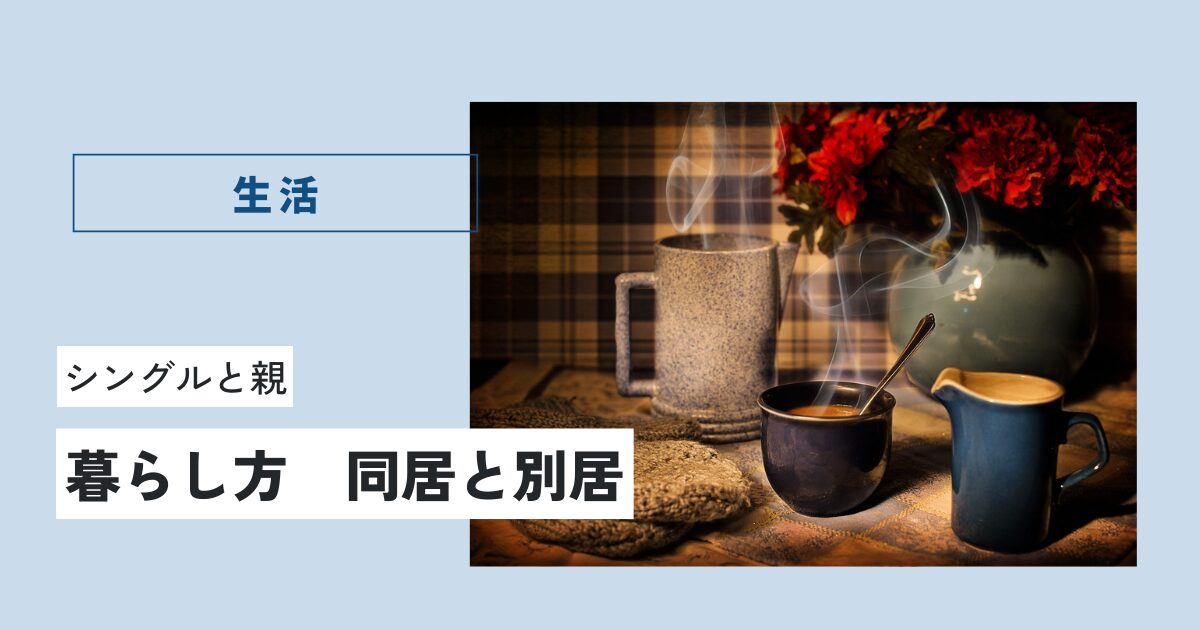【シングルと親の生活】高齢の親と同居生活10のポイント:準備から日常生活まで:40代独身女性体験談

2025年2月更新
こんにちは!このブログにお越しいただきありがとうございます。
40代シングル女性のあおこです。2024年に実家じまいを行い、現在は高齢の両親と3人暮らしをしています。
このページでは、「高齢の親との同居に関する10の重要なポイント」について、私の体験をもとにお伝えします。
高齢の親との同居について悩んでいませんか?1年前の私がそうでした。
同居生活には想像以上の課題がたくさんあります。
なぜなら、生活習慣の違いや価値観の相違が日々の生活で顕在化するからです。
私も試行錯誤の連続ですが、1年前に両親との同居を始め、今は穏やかな生活を送れています。
この記事を読むと、同居生活で直面する可能性のある問題とその解決策を知ることができ、
スムーズな同居生活のスタートを切られるようになります。
お互いの理解と尊重、そして適切なコミュニケーションが、高齢の親との円滑な同居生活の鍵
となります。
・特に重要だと思った順に星
・シングルならではの視点を「シングルポイント」として記載しました。
01. 同居を決意:高齢の親との同居を考える理由と準備
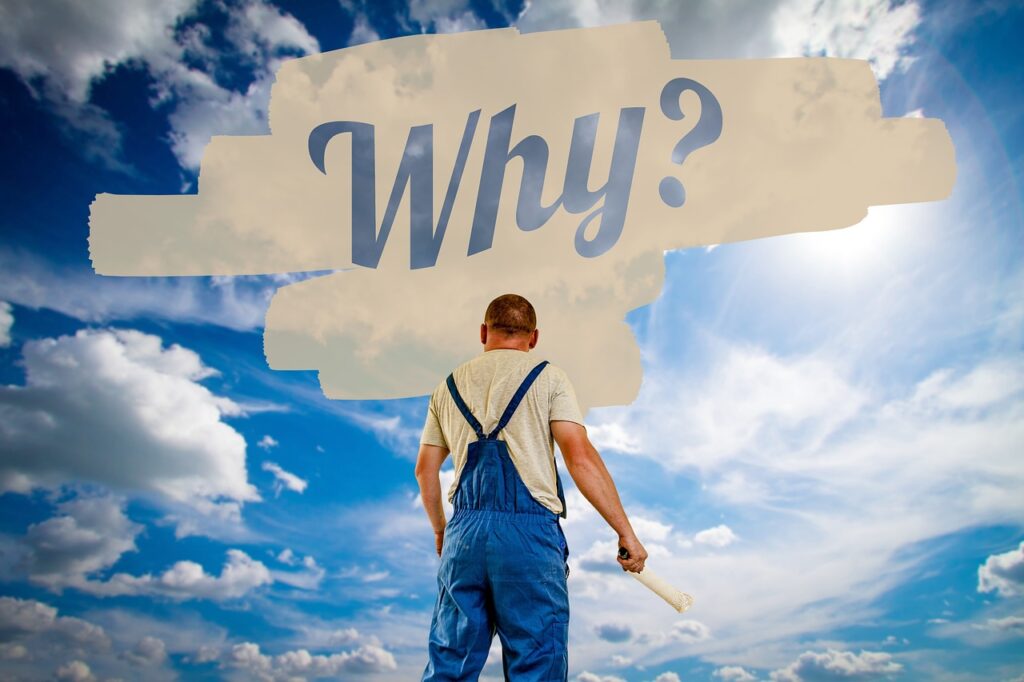
高齢の親との同居は大きな決断ですが、適切な準備と心構えがあれば、家族の絆を深める素晴らしい機会となります。特にシングルの方は、自分の将来も見据えながら、バランスの取れた同居生活を目指しましょう。
高齢の親との同居を決意することは、大きな人生の転換点です。
同居を考える主な理由は以下ようのなことが挙げられます。
- 親の健康状態の悪化
- 遠距離介護の限界
- 経済的な理由(親の年金だけでは生活が厳しいなど)
- 親の孤独感の解消
- 将来の介護に備えて
- 親の高齢化による家のメンテナンス負担増

あおこ家では「お母さん、毎日何をしているんだろう。って思って」という母の一言をきっかけに実家じまいを考え、同時に同居も考え始めました。
何気ないことでも親の話していることに耳を傾け、なぜその様な話をしているのかを聞いてみることが大事だと感じています。
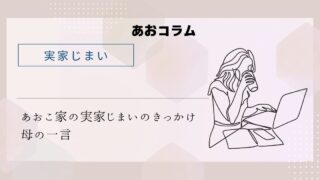
同居を検討した際には以下の様なことを準備として考えました。
同居前の準備チェックリスト
家族での話し合い
家族の未来について、どの様な生活をしたいのか。
メリット、デメリットだけではなく、それぞれの気持ちを素直に話し合うことが大事です。
- 同居の目的と期待を共有
- それぞれの不安や懸念点を率直に話し合う
生活スタイルの確認
高齢の親との生活は、特に生活の時間帯が異なる場合が多いです。
ですが、生活リズムを合わせたり変えたりすることは難しいです。
まずはお互いの現状の生活スタイルを確認して、
お互いにできるだけ心地よく生活するためにはどうしたら良いかを考えましょう。
- 生活リズム、食事の好み、趣味など
経済面の計画
同居する場合、生活費の分担方法はとても重要です。同居を始める前に生活費の分担をどうするか、きちんと話し合いをしておきましょう。
将来の親の介護費用も考慮して、介護費用は親の財産で賄えそうか含め確認しましょう。
介護費用は基本的には親の財産で対応することを考えましょう。
同居を決意し、準備を進める過程は、家族の絆を深める良い機会にもなります。
慎重に、前向きに準備を進めることで、より円滑な同居生活のスタートを切ることができます。
親との同居前に一人暮らしをしていた方も多いのではないでしょうか?
私もそうでした。一人の生活から同居することで窮屈に感じないか?両親も私もお互い負担にならないか?と悩みました。
例えば両親は早寝早起き、私は夜が遅く生活リズムが異なる点が一番心配でした。
そこで私はお互いの生活リズムをできるだけ保つことのできるよう、それぞれに個室と共同スペースがある物件を探すことを解決策の一つとして物件を探しました。

同居を決める時に同居してみて、ダメならまた別々に暮らせば良い。というある種の開き直りをして、両親にも伝えました。
同居前に気持ちを伝えたことで、お互いにもしダメでもまたその時に考えれば良い。と思えられ、気持ちを楽にできました。

02. 物件探し:高齢者と同居するための理想的な住まい選び

高齢の親との同居生活を快適に送るためには、適切な物件選びが非常に重要です。
物件選びが同居にあたって一番初めの重要ポイントだと言えます。
家族全員のニーズを満たし、将来の変化にも対応できる住まいを選ぶことが、長期的な同居生活の成功につながります。
高齢者と暮らす場合には、一人暮らしとは異なり、バリアフリーなど、将来の介護を視野に入れが物件探しも重要です。また近くに医療機関があるかも大きなポイントになります。
物件選びの重要ポイント
バリアフリー設計
- 段差の少ない間取り
- 手すりの設置(特にトイレ、浴室、階段)
- 広めの廊下や開口部(車椅子対応)
十分な広さと個室の確保
- 家族全員の個室を確保できる間取り
- リビングなどの共有スペースの広さ
立地条件
引越しは車を手放すきっかけにもなります。
そのためには医療機関へのアクセスや公共交通機関の利用のしやすさも重要なポイントです。
- 医療機関へのアクセス
- 買い物の利便性
- 公共交通機関の利用しやすさ
将来の介護を考慮した設備
- 介護用ベッドが入る広さの寝室
- 車椅子で使用可能な洗面台やキッチン
セキュリティ
同居する場合でも、高齢になると特にいつなにが起こるかわかりません。子が不在時に親の体調が悪くなることも考えられるため、住居に緊急通報システムがあると安心です。
- 防犯設備の充実
- 緊急通報システムの有無
自然環境
将来の介護も見越して、家にいる時間が長くなった場合でも、できるだけ気持ちを明るく保てるように。日当たりの良さや騒音の少なさ、窓からの眺めなど、家にいて外の自然を感じられる環境も重要です。
- 日当たりの良さ
- 騒音の少なさ
- 緑地や公園の近さ
災害の発生のしやすさの確認
高齢になると災害があった場合でも、すぐに避難することが困難になる可能性があります。
可能な限り、災害の少ない場所を選ぶことが望ましいです。
- 近くに海や川、山があるか
- 地震が発生しやすい地域か
- 雪や大雨、台風などが起きやすい地域か
物件探しの手順
家族での話し合い
- 必要な条件や予算を明確にする
- 各自の希望を共有し、優先順位をつける
情報収集
- 不動産ウェブサイトでの物件検索
- 地域の不動産会社への相談
現地見学
- 複数の物件を比較検討
- 家族全員で見学し、意見を出し合う
周辺環境の確認
- 実際に周辺を歩いて、生活のしやすさを確認
- 可能な限り、朝・昼・夜の住環境がどうか、時間を分けて確認
大家さんへの相談と交渉
- 設備の変更・追加の相談

以下のことを大家さんと交渉し、ご対応いただきました。叶わなかった要望もありましたが、ダメ元でも家族の要望は大家さんに伝えることをお勧めします。
対応いただいた内容
- トイレのウォシュレットをつける
- 畳のおもて替え
対応いただけなかった内容
- キッチンをオール電化にする:工事が大掛かりになるため
- 全ての部屋にエアコンをつける:室外機の置き場所がないため
- 将来の変化を想定する
- 5年後、10年後の家族の状況を考慮して選ぶ
- 予算オーバーに注意
- 十分な時間をかけて検討し、慎重に決定する
- 家族のストレスを減らすことを優先する
一人暮らしの物件探しに比べ、高齢の親との同居は考慮すべき点も増えます。
同時に親の気持ちだけでなく、自分自身がどう暮らしていきたいか。
という自分の心地よさも大事に物件探しをしました。
また、物件の契約は、親名義ではなく、自分の名義で全て契約しました。
以下のことを考えたためです。
・両親は年金生活のため、審査が難しい
・両親に何かあっても名義変更の手続きなどが不要になるため
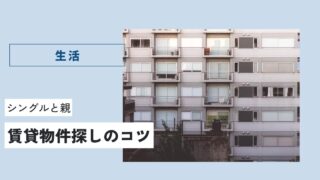
03. 引越し:スムーズな転居のためのチェックリスト

高齢の親との同居を始める際の引越しは、通常の引越しよりも慎重な準備と配慮が必要です。
親の身体的・精神的負担を最小限に抑えながら、新生活へのスムーズな移行を実現することが
重要です。
引越しは大きなイベントですが、事前にしっかりと準備を進めることで、ストレスを軽減できます。
引越し準備のポイント
十分な準備期間の確保
- 可能な限り、家族の体調への負担が少ない春や秋に行う
- 親の体調や心理的準備に配慮しながら進める
不用品の整理と処分
- 親と一緒に思い出の品を整理する時間を設ける
- 必要なものと不要なものを明確に区分する
新居のレイアウト計画
- 家具の配置を事前に決める
- 親の使い慣れた家具や道具の配置を優先する
引越し業者の選定
- 高齢者の引越し経験が豊富な業者を選ぶ
- 割高にならない業者を選ぶ
家族内の役割分担を明確にする
- 引越し業者との調整や引越し当日の役割を明確にしておく
引越し当日のチェックリスト
両親の体調確認
- 十分な睡眠と食事を取ってもらう
- 必要な薬を手元に用意する
重要書類の管理
- 保険証、年金手帳などの重要書類は別途管理する
- 貴重品は自分で運ぶ
環境の変化への配慮
- 使い慣れた寝具や日用品をすぐに使えるよう準備する
引越しの荷物にラベリングし、すぐに使うものはわかる様にする
休憩スペースの確保
- 親が疲れた時に休める場所を確保する
- 水分補給や軽食を準備しておく
引越し当日は調理する余裕がないことが多いです。あらかじめ水分や調理済みの軽食を準備しておき、栄養補給と休憩ができる様にしましょう。
- 無理をしない
- 親の体調や気分に合わせて、柔軟に対応する
- 大切な思い出の品は丁寧に扱い、新居でも適切に配置する
- 環境の変化によるストレスを減らす準備をしておく
- 役割分担を決めておく
円滑な引越しは、高齢の親との新しい同居生活のスタートを良いものにする重要な要素です。
十分な準備と配慮を行い、家族全員が安心して新生活を始められるようサポートしましょう。
一人暮らしをしていた私が新居に先に引っ越し、生活環境を整えた後で、両親に引っ越してもらうスケジュールとしました。
結果、両親の引越し当日から、最低限の生活はできる状態であったので、新しい生活がスムーズに始められました。

実家じまいの関係で夏に引越しをしたため、とても大変でした。
まだエアコンもついていない部屋で汗だくで一人準備をしたことが思い出です。可能な限り、体に負担の少ない季節に引越しされることをお勧めします。
04. 新生活スタート:同居初期に決めるべき生活ルール

高齢の親との同居生活を円滑に進めるためには、生活におけるルールの設定が不可欠です。
お互いの生活スタイルや価値観を尊重しながら、共通の理解を築くことが重要です。
ですが、初めから細かく決めすぎず、見直すことを前提にしましょう。
主要なルール設定項目
プライバシーの尊重
個室に入る時にはノックする。や、宅配の荷物が届いた場合は、本人以外は開けない。などプライバシーを尊重するルールを決めましょう。
- 個室への入室ルール
- 個人の所有物の取り扱い
家事分担
- 食事の準備と後片付け
- 掃除や洗濯の分担
- ゴミ出しの担当
経済的な取り決め
- 生活費の分担方法
生活リズム
- 起床・就寝時間の尊重
- 食事時間の設定
- お風呂の順番
外出・旅行
- 外出時の連絡ルール
- 長期不在時の対応
- 過度に厳格にならない
- ルールは生活をスムーズにするためのもの。窮屈になりすぎないよう注意する
- 個人の自由を尊重する
- 必要以上に干渉しないよう、適度な距離感を保つ
- 親世代と子世代で常識が異なる場合があることを認識し、互いに歩み寄る

特に重要だったのは、プライバシーの尊重と家事分担に関するルールです。例えば、個室への入室は必ずノックをすることや、食事の準備は当番制にするなど、具体的なルールを決めました。
これにより、お互いの生活リズムを尊重しながら、協力して家事を
行うことができるようになりました。
05. 経済面:同居生活における費用分担と世帯分離の
メリット

高齢の親との同居では、生活費の管理と分担も重要な課題となります。適切な分担方法を決めることで、経済的なストレスを軽減し、円滑な同居生活を送ることができます。
また、世帯分離を検討することで、さらなる経済的メリットを得られる可能性があります。
適切な生活費の管理と分担、そして世帯分離の検討は、同居生活の経済的安定につながります。家族で十分に話し合い、家族にとって最適な選択をすることが大切です。
生活費の分担方法
収入比での分担
- それぞれの収入に応じて分担する方法
- 公平感があるが、計算が複雑になる可能性がある
固定額での分担
- 毎月一定額を決めて分担する方法
- シンプルだが、収入の差が大きい場合は不公平感が生じる可能性がある
項目別での分担
- 食費、光熱費、家賃などの項目ごとに分担する方法
- 細かい管理が可能だが、手間がかかる
均等に分担
- 全ての項目を均等に分担する方法
- 計算が簡単になる

均等に分担を選択しました。均等に費用を負担して、
共通のお財布から生活費を利用する形です。
支払いや予実の管理も簡単でシンプルになるため選択しました。

世帯分離のメリット
世帯分離とは、同じ家に住んでいても、住民票上で別世帯として扱われることを指します。
以下のようなメリットがあります:
税金面での優遇
- 所得税や住民税が別々に計算されるため、全体的な税負担が軽減される可能性がある
- 扶養控除を受けられる場合がある
社会保障制度の利用
- 親の収入が低い場合、介護保険料や国民健康保険料が軽減される可能性がある
- 高齢者向けの福祉サービスを受けやすくなる
年金受給への影響
- 年金受給額が増える可能性がある(子との同一世帯では減額されるケースがある)
世帯分離のデメリット
手続きの煩雑さ
- 世帯分離の手続き自体に時間と労力がかかる
- 各種手続きを別々に行う必要がある
家族割引の適用外
- 携帯電話の家族割引など、同一世帯でないと適用されないサービスがある
- 共同の口座を作る
共通の支出用に別口座を作ることで、管理が容易になります - 予算を立てる
月ごとの予算を立てることで、無駄な支出を抑えられます - 定期的な見直し
- 緊急時の備えを考えておく
- 世帯分離も検討する
06. 心の準備:ストレスを軽減し、良好な関係を築く
コツ

高齢の親との同居生活では、ストレスを感じることも少なくありません。
自分の時間や空間を確保し、適切にストレスを管理することが、長期的に良好な関係を維持するためのカギとなります。特に同居になると小さなストレスの積み重ねが大きな亀裂に変化してしまうこともあります。そのため、あらかじめストレスの原因を知り、自分なりの対策を持っておくことが重要です。
ストレスの主な原因
- プライバシーの侵害
- 生活リズムの違い
- 価値観の相違
- 介護負担の増加
- 自由時間の減少
ストレス管理と個人時間確保のポイント
個室と「自分の時間」の確保
- 可能な限り、自分だけの空間と「自分の時間」を確保することが重要です
一人でできるストレス解消法の確立
- 運動、瞑想、読書など、自分に合ったストレス解消法を見つけましょう
- 家の中でできるリラックス方法も用意しておくと良いでしょう

自分の部屋にいる時には好きな音楽を聞いたり、本を読んだり
好きな香りのディヒューザーを置いたりして、リラックスするようにしています。
外出の機会を作る
- 週末や休日は外出し、気分転換を図りましょう
- 両親と一緒の外出も計画し、新鮮な体験を共有することで関係性を深められます
友人や専門家への相談
- 一人でストレス解消するだけではなく、友人や地域のケアマネージャなどの専門家に話を聞いてもらうだけでも心が軽くなります。
一人で抱え込まずに、誰かに話をしてみましょう。
違和感を我慢せず、その場で伝える
- 生活の中で感じた違和感をためたり、我慢せずに、感じた時点で伝える様にしましょう。違和感や不満をためたり我慢していると、いつか我慢しきれない状態になり、
家族のバランスが取れなくなります。
- 個室と「自分時間」の確保
- 一人でできるストレス発散のポイント
- 外出の機会を作る
- 友人や専門家に相談する
- 違和感を我慢せず、その場で伝える

久しぶりに一緒に生活してみると、考え方の違いや、小さな生活習慣に違和感や嫌だなと思うことが出てきました。
初めは我慢していたのですが、徐々に気持ちがしんどくなってしまいました。このままでは同居自体が難しくなってしまうと考え、それからは気持ちを溜めたり我慢したりせずに、その場で伝える様になりました。
両親に対しても、嫌なことや、何か思うこと、してほしいことがあれば、言葉で伝えてもらうにお願いしています。
07. 新しい習慣:同居後に始めた家族の絆を深める工夫

高齢の親との同居生活を始めると、これまでの生活習慣が大きく変わります。
この機会に、家族全員で新しい習慣を作ることで、より豊かで充実した同居生活を送ることができます。
家族全員が楽しみめる習慣を見つけ、継続することで、健康的で前向きな生活を送ることにもつながります。時には試行錯誤も必要ですが、自分たちらしい習慣を作っていく過程がかけがえのない思い出となるでしょう。
新しい習慣づくりの意義
- 家族の絆を深める
- 共通の話題や楽しみを増やす
- 健康的な生活リズムを確立する
- 新しい生活への適応をスムーズにする
おすすめの新しい家族習慣
健康的な朝の習慣
朝であれば、仕事前に時間を合わせて一緒に運動したり、朝食を取ったり決まった時間に一緒に活動をしやすいです。
- 朝にウォーキングや散歩の運動を行う
- 健康的な朝食を一緒に準備し、食べる
家族での趣味の時間
- 園芸、読書、ゲームなど、共通の趣味を見つける
- 定期的に一緒に楽しむ時間を設ける
思い出を記録に残す
- 家族で外出や特別な活動を計画する
- 家族の思い出を写真や動画に残す
外出や仕事の予定を共有する
- カレンダーやアプリを利用して予定を共有する
一緒に出かける
- 外食や温泉などに一緒に出かける
- 強制しない
無理に参加をしいいると、逆効果になる可能性がある - 体力や体調を考慮する
- 家族の時間と個人の時間のバランスを取る

私達は同居を始めてから以下の習慣を始めました。新しい習慣を始めたことで、両親との会話も増えました。また、今まで両親の写真や動画をあまり撮っていなかったため、何気ない日常でも気づいた時に記録する様にしています。
- 朝のウオーキング
- お昼は可能な限り一緒に食べる
- 思い出を写真や動画に残す
08. 介護への備え:将来を見据えた生活設計

高齢の親との同居生活において、将来の介護に備えることは非常に重要です。
早い段階から準備を始めることで、突然の事態にも冷静に対応でき、親にとっても子にとっても負担の少ない介護環境を整えることができます。
介護への備えの重要性
- 突然の事態に慌てずに対応できる
- 経済的な準備ができる
- 適切な介護サービスを選択できる
- 家族の負担を軽減できる
- 親の希望を尊重した介護計画を立てられる
介護への備えのステップ
家族での話し合い
- 親の希望(在宅介護か施設介護かなど)を確認する
- 家族の介護への関わり方を決める
情報収集
- 介護保険制度について学ぶ
- 地域の介護サービスや施設について調べる
- 介護に関するセミナーや講座に参加する
経済的な準備
- 介護保険や民間の介護保険を検討する
- 親の貯蓄状況を確認しておく
住環境の整備
- バリアフリー化の検討
- 介護用品の設置スペースの確保
- 将来的なリフォームの可能性を考慮する
介護スキルの習得
- 基本的な介護技術を学ぶ
地域とのつながり
- 地域の高齢者サービスや支援制度を把握する
仕事との両立計画
- 介護休業制度について確認する
- 在宅勤務の可能性を探る
- キャリアプランを見直す
緊急時の対応準備
- 緊急連絡先リストの作成
- かかりつけ医や利用したい病院の確認
- 親の自尊心を傷つけない。親の気持ちに配慮する
- 普段から介護が必要になった際の希望を会話しておく
- 地域のサポートなど活用できるものは活用する前提で考える
- 家族と仕事のバランスをとり、自分自身のケアと将来も大切に考える

介護が必要になった時に、どのような対応をしてほしいか、普段から両親と会話する様にしています。
事前に準備しておくことで、いざ対応が必要になった時にもお互いに納得した対応ができると考えるからです。
介護については、「親子の終活」の方で今後記事にしていきます。
09. 心のケア:高齢の親に優しく接するためのマインドセット

高齢の親との同居生活では、日々の接し方や心のケアが非常に重要です。
親の尊厳を守りながら、適切なサポートを提供することで、お互いに心地よい関係性を築くことができます。
高齢になるにつれ、できないことが増えてくるので、子供からすると、イライラしてしまったり、キツく当たってしまったりすることもあるかもしれません。
でもそれは将来自分も通る道。できるだけ心に余裕を持ち優しく接することができるようなマインドセットを行いましょう。
高齢の親との同居生活は、課題も多いですが、お互いに成長できる貴重な機会でもあります。日々の小さな気づかいと感謝の気持ちを大切に。
高齢の親への接する際のマインドセット
尊重と敬意を示す
- 親の人生経験や知恵を尊重する
- 意見や好みを尊重し、強制しない
耳を傾ける
- 親の話をじっくり聞く時間を設ける
- 批判や否定をせず、共感的に聞く
自立を促す
- できることは自分でしてもらう
- 過度な手助けは避け、見守る姿勢を大切にする
コミュニケーションを大切にする
- 日々の会話を大切にする
- 顔色や食事の際の様子なども気にかける
感謝の気持ちを言葉で伝える
- 日々の小さなことにも感謝の言葉を伝える
- 親の貢献や努力を認め、言葉で表現する
- 親の姿は将来の自分の姿だと思って接する
- 親の考えを尊重する
- できることは自分でしてもらい、見守る姿勢を大切にする
- 普段からコミュニケーションをとり、小さな変化にも気づける様にする
- 感謝を言葉で伝える

私は当初、両親の生活に過度に干渉してしまい、お互いがモヤモヤしてしまうことがありました。
しかし、両親の自立心を尊重し、見守る姿勢に切り替えたことで、モヤモヤが改善し、ストレスが減りました。
基本的には、お互いの自尊心を尊重して、できることは自分でやる様にすることが大事だと感じています。
10. シングルと親の生活を充実させるためのポイント

高齢の親との同居生活は、試行錯誤の連続です。これまで様々な側面から同居生活のポイントを見てきましたが、最後に、長期的な視点で同居生活を充実させるためのポイントについて考えてみましょう。日々の小さな工夫と長期的な視点を持つことで、より豊かで充実した生活を実現することができます。
最も大切なのは、お互いを思いやり、尊重し合う気持ちです。同居生活は決して楽ではありませんが、適切な準備と心構えがあれば、かけがえのない経験となります。同居生活の長期的な目標
同居生活を充実させるためのポイント
課題や問題があれば家族で話合う
- 問題点や改善点を率直に話し合う
柔軟性と適応力の維持
- 家族の状況変化に柔軟に対応できる体制を整える
- 新しい生活スタイルや技術の導入に前向きになる
個人の時間と家族の時間のバランスを取る
- それぞれのプライバシーと個人の時間を尊重する
- 家族で過ごす質の高い時間も大切にする
健康管理の習慣化
- 運動や健康的な食事を家族で楽しむ
財務計画の定期的な見直し
- 長期的な経済的安定のため、定期的に家計を見直す
- 将来の介護費用なども考慮に入れる
介護に関して事前に話し合う
- 将来の介護について、事前に話し合っておく

実際に同居してみて以下の様なことが特に大切だと感じています。
- コミュニケーションを大切にする
- 柔軟性を持つ
- 専門家や地域のサポートも頼る
- 親だけではなく自身のケアも大切にする
- 前向きなマインドセットで対応する
高齢の親との同居生活は、悩みの連続です。しかし、適切な準備と心構えがあれば、家族の絆を深め、互いに成長できる素晴らしい機会となります。
私もまだまだ試行錯誤の連続ですが、私の経験が誰かの参考になれたら嬉しいです。
これからも親との同居生活で感じたこと、学んだことなどを記事にしていきます。