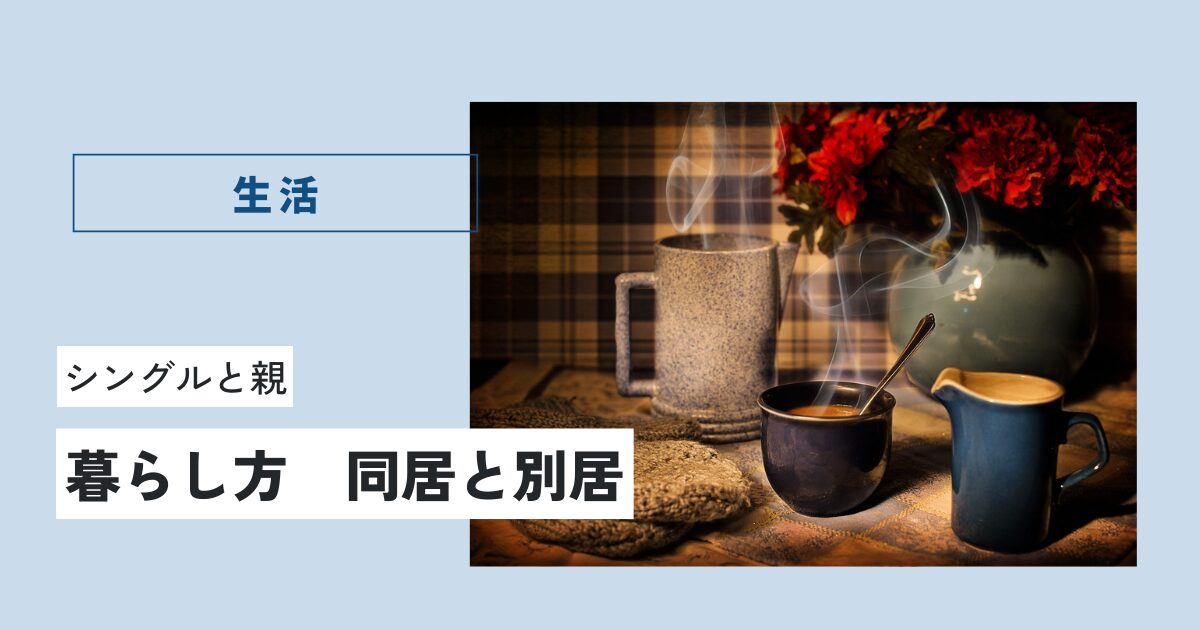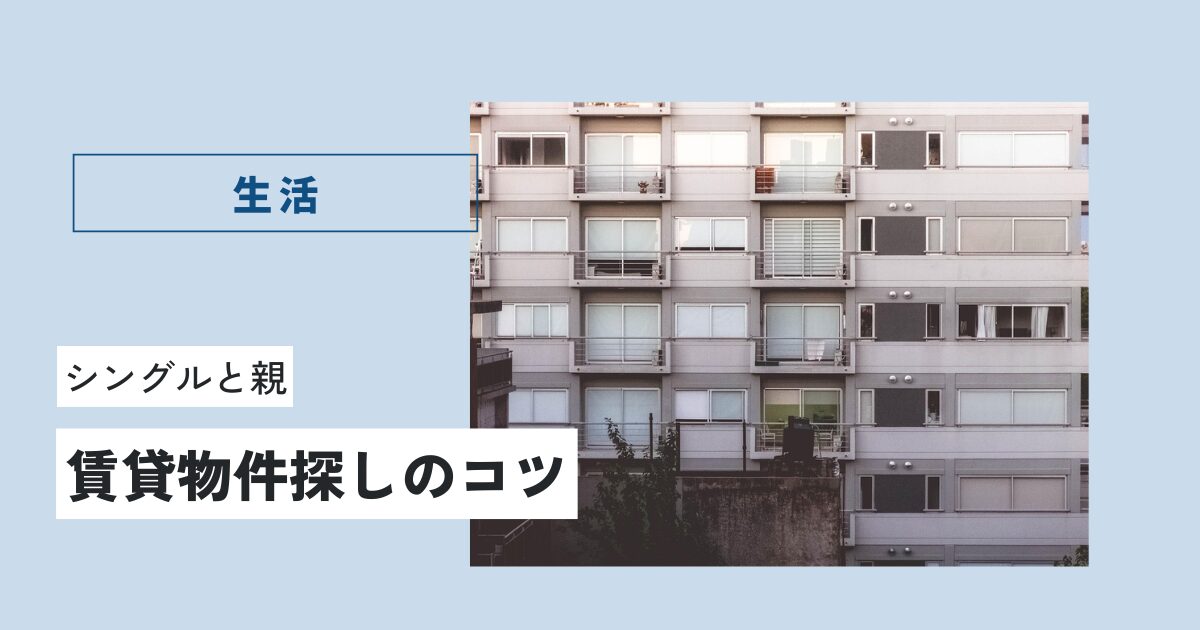【シングルと親の生活】親との同居で生活費を賢く節約する方法8選

親と同居を始めたけれど、思わぬ出費に頭を悩ませていませんか?
高齢の親との同居生活では、適切な家計管理と節約術が不可欠なのです。
なぜなら、親世代と子世代では生活習慣や価値観が異なり、予想外の支出が発生しやすいからです。
私は40代シングル女性として、2024年に実家じまいを経験し、両親との3人暮らしを始めました。
この記事では、私の体験を基に、高齢の親との同居生活で効果的な生活費の節約方法をお伝えします。私も同居をし始めた当初は一人暮らしの時よりも生活費が上がってしまいましたが、以下に記載した方法を実践したことで、現在は一人暮らしの時に比べて3分の2程の生活費で賄える様になりました。
この記事を読むと、具体的な節約テクニックを学べ、家計の負担を軽減できるようになります。
01. 電気・ガス会社の見直しで大幅節約

電気・ガス会社の見直しは、同居生活での大きな節約ポイントです。特に、電力自由化以降、選択肢が増えたことで、家族の生活パターンに合わせた最適なプランを選べるようになりました。
電気・ガス会社の見直しは、年間で数万円の節約につながる可能性があります。家族で使用状況を確認し、最適なプランを選びましょう。
見直しは面倒ではありますが、一度実施すればそれ以降節約が継続でき、費用も大きく下がる可能性もあります。
電力会社の選び方
- 使用量の把握: まずは、1年間の電気使用量を確認します。
- 比較サイトの活用: 複数の電力会社のプランを比較できるサイトを利用します。
- 時間帯別料金の検討: 在宅時間が長い場合、時間帯別料金が有利な場合があります。
- 再生可能エネルギーの検討: 環境に配慮したプランを選ぶことで、長期的なコスト削減につながることもあります。
ガス会社の見直し
- オール電化の検討: 電気代とのトータルコストを計算し、オール電化が有利か確認します。
- ガス機器の効率化: 高効率給湯器への交換で、ガス代を20%程度削減できる場合があります。
- セット割の活用: 電気とガスをセットで契約すると、割引が適用されるプランもあります。

比較サイトを利用して、いろいろなパターンごとの費用を確認し、電力会社とガス会社を見直し、統一したことで、費用の節約に成功しました。
一人暮らしの時はあまり費用も確認できていませんでしたが、同居する様になり毎月の費用も確認する様になりました。
02. 携帯電話代を抑える:格安スマホへの切り替え

携帯電話代は、家計の中でも大きな割合を占める固定費の一つです。特に、高齢の親が長年使い慣れた大手キャリアのプランを継続している場合、不必要に高額な料金を支払っていることがあります。
格安スマホへの移行は、初期費用が発生する場合があるため、長期的な視点で判断することが大切です。また、高齢者が使いこなせるか不安な場合は、試用期間のあるプランを選ぶのも一案です。
電気・ガスの費用と同様、スマホのキャリア見直しも面倒ではありますが、一度実施すればそれ以降節約が継続でき、費用も大きく下がる可能性が大きいです。
格安スマホへの切り替えのメリット
- 月額料金の大幅削減: 大手キャリアの半額以下になることも珍しくありません。
- 必要な機能に絞ったプラン: 使用頻度の低い機能を省いたシンプルなプランを選べます。
- 契約期間の縛りなし: 多くの格安スマホは、長期契約の縛りがないため、柔軟に変更可能です。
格安スマホ選びのポイント
- 通信品質の確認: 利用エリアでの通信品質を事前にチェックします。
- サポート体制: 特に高齢者向けには、手厚いサポートがある会社を選びましょう。
- 端末の選択: 使いやすさを重視し、シンプルな操作の端末を選びます。
- 家族割の活用: 家族でまとめて契約すると、さらにお得になるプランもあります。

両親は長年大手キャリアを利用していましたが、同居を機に格安スマホに変更しました。2人合わせて月額1万円以上の節約になりました。
また、将来のことを考慮して、両親のスマホも私名義で契約し、それを使ってもらう形に変更しました。
親のスマホを子供名義に変更し、格安スマホに変更する手順
親のスマホキャリアを子供名義に変更し、さらに格安スマホに変更する手順は、いくつかのステップを踏む必要があります。以下に一般的な流れを説明します。
キャリアや契約内容によっては手続きが異なる場合もありますので、詳細はキャリアに確認することをおすすめします。
1. 親のスマホ契約を子供名義に変更
親のスマホ契約を子供名義に変更するためには、契約者名義変更の手続きが必要です。
手順は以下の通りです。
必要な書類:
- 親の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 子供の本人確認書類
- 契約者変更に必要な書類(キャリアによって異なります)
手続き方法:
- キャリアのショップまたはオンラインで手続き
- まず、現在契約しているキャリア(例:ドコモ、au、ソフトバンクなど)の店舗に行くか、オンラインで契約者名義変更の手続きを行います。
- 親と子供が一緒に来店することが求められる場合があります。
- 名義変更手続き
- 親から子供への名義変更手続きを行います。この時に、引き継ぐプランやサービスの詳細も再確認することが重要です。
- 契約者名義変更が完了するまで待つ
- 名義変更が完了するまでに数日かかる場合があります。その間に、キャリアからの確認連絡などが来ることもあります。
2. 子供名義で番号を引き継いで格安スマホに変更
親名義の契約を子供名義に変更した後、格安スマホに変更する流れは次のようになります。
必要な手続き:
- 新たに契約する格安SIMの契約
- 申し込みに必要な書類(身分証明書など)
手続き方法:
- 格安スマホの選定
- 自分に合った格安スマホのプランを選びます。料金、データ通信量、通話オプションなどを比較して決めましょう。
- MNP(モバイル番号ポータビリティ)を使って番号を引き継ぐ
- 親の契約を子供名義に変更した後、格安スマホへ移行する場合、現在使っている番号をそのまま引き継ぐためには、MNP(モバイル番号ポータビリティ)を利用する必要があります。
- 現在のキャリアからMNP予約番号を取得します。これはオンラインまたは店舗で手続きできます。MNP予約番号は通常15日間有効です。
- 格安SIMの申し込み
- MNP予約番号を持って、格安スマホを提供している会社のウェブサイトや店舗で契約手続きを行います。
- 契約時にMNP予約番号を伝えて、現在の番号をそのまま引き継ぎます。
- SIMカードの受け取りと設定
- 格安SIMが届いたら、スマホにSIMカードを差し込み、APN設定を行います。これにより、インターネット通信が利用可能になります。
- キャリアメールの引き継ぎ(必要な場合)
- キャリアメール(@docomo.ne.jpや@softbank.ne.jpなど)を引き継ぎたい場合、格安SIM会社によっては、キャリアメールの移行に対応していない場合があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
3. 契約内容の確認と変更
- 格安スマホへの変更後も、旧契約に残っている割引やサービスがあれば、変更時に確認し、最適なプランを選んでください。
- 料金やサービス内容を見直し、無駄のないプランに変更することも検討しましょう。
03. インターネット料金を削減:格安Wifiの活用

インターネットは現代生活に欠かせませんが、その料金は家計の大きな負担になることがあります。特に、親世代と同居する場合、それぞれの使用状況に合わせた最適なプランを選ぶことが重要です。
格安Wifiのメリット
- 月額料金の削減: 大手プロバイダと比べて、30%以上安くなることもあります。
- 契約の簡便さ: 多くの場合、オンラインで簡単に契約できます。
- 工事不要: 機器を設置するだけで使用可能な場合が多いです。
- 持ち運び可能: ポケットWifiタイプなら、外出先でも使用できます。
格安Wifi選びのポイント
- 通信速度の確認: 動画視聴やオンライン会議など、用途に応じた速度を確保します。
- データ容量: 使用量に合わせたプランを選びましょう。
- カバーエリア: 特に地方在住の場合、利用可能エリアを確認します。
- セキュリティ機能: 個人情報保護のため、セキュリティ機能が充実しているものを選びます。

実家の際は固定回線を契約していましたが、Wifi付きの賃貸を借りたことで、Wifiの費用としては無料になりました。
Wifi付きの賃貸物件を借りることも節約になります。
04. 食費の節約:ネットでの購入と調理の工夫

食費は生活費の中でも大きな割合を占める支出です。親との同居では、食事の好みや習慣の違いから無駄が生じやすくなります。効果的な食費節約には、計画的な購入と調理の工夫が欠かせません。
食事は健康に直結するため、節約だけでなく栄養バランスにも注意を払いましょう。また、高齢者の場合は咀嚼や消化を考慮した調理方法を心がけることも大切です。
ネット購入のメリット
- まとめ買いによる割引: 大容量パックの購入で単価を抑えられます。
- 食品ロスの削減: 店舗での購入に比べ必要な物だけ購入することで、廃棄を減らせます。
- 買い物頻度の減少: 時間と交通費の節約にもつながります。
調理の工夫
- 計画的な献立作り: 週単位でメニューを決め、効率的に食材を使い切ります。
- 作り置きの活用: 一度に大量調理し、冷凍保存することで時間と光熱費を節約。
- 季節の食材の利用: 旬の食材は栄養価が高く、比較的安価です。
- 食べ残しのリメイク: 創意工夫で新しい料理に生まれ変わらせます。

節約も大事ですが、食事は生活の中の楽しみでもあります。
節約を意識しつつもそれぞれが食べたいものを食べられるように、毎週それぞれが気分転換と運動のためにも1回は買い物に行き、食べたいものを買ってきたり、調理したりする様にしています。
05. 医療費の管理:健康保険と医療費控除の活用

高齢の親との同居では、医療費の管理が重要な課題となります。適切な健康保険の選択と医療費控除の活用により、家計への負担を軽減できます。
医療費の管理は、単なる節約だけでなく、家族の健康状態の把握にもつながります。定期的な健康チェックと、適切な医療サービスの利用を心がけましょう。
健康保険の最適化
- 後期高齢者医療制度の理解: 75歳以上の場合、この制度が適用されます。
- 高額療養費制度の活用: 医療費が一定額を超えた場合、払い戻しを受けられます。
- 付加給付の確認: 健康保険組合によっては、独自の給付がある場合があります。
医療費控除の活用
- 領収書の管理: 年間の医療費をまとめて記録します。
- 対象範囲の確認: 医薬品や介護サービスなども含まれる場合があります。
- セルフメディケーション税制の利用: 特定の医薬品購入で税制優遇を受けられます。
06. 趣味や娯楽の共有:家族で楽しむ節約術

高齢の親との同居生活では、趣味や娯楽の時間を共有することで、精神的な充実感を得ながら、支出を抑えることができます。家族で楽しめるアクティビティを見つけることは、節約だけでなく、絆を深める良い機会にもなります。
趣味や娯楽の共有は、金銭的な節約以上の価値をもたらします。家族それぞれの興味や体力に合わせて、無理のない範囲で楽しめるアクティビティを選びましょう。
家族で楽しめる節約アクティビティ
- 家庭菜園: ベランダや庭で野菜を育てることで、食費節約と趣味を両立。
- DIYプロジェクト: 家具のリノベーションや小物作りを家族で楽しむ。
- ボードゲーム: 一度購入すれば何度でも楽しめる経済的な娯楽。
- 地域イベントへの参加: 多くの場合無料や低価格で参加できる地域の催し物。
- 自然散策: 近隣の公園や自然スポットでのウォーキングや写真撮影。
趣味の共有によるメリット
- コミュニケーションの活性化: 共通の話題が増え、家族の会話が豊かになります。
- 健康増進: 適度な運動や外出の機会が増えることで、心身の健康維持につながります。
- 新しい発見: 世代を超えて趣味を共有することで、新たな視点や興味が生まれます。

同居を始めてから運動不足解消と体力作りのために始めたウォーキングは気分転換にもなり、とても良い習慣になりました。
ウォーキング以外でも家の中の小さなDIYを一緒に行ったり、より良い暮らしを一緒に作っていく様にしています。
07.買い物の時に本当に生活に必要なものか?または気持ちを豊かにしてくれるものか?考える

インタネットや街でお店を見ていると、欲しいな。と思うもので溢れています。しかし、ものを使う人の人数は限られているので、「本当に生活に必要なものか?」本当に必要でないものでも「気持ちを豊かにしてくれるものか」を考えましょう。
また、シングルは特に、将来を考慮して、家具や家電の購入の際にも、一人で動かしたり処分できるものか?を考えるのも重要です。
購入するものが、リセール(再販)しても価値があるものかも考えましょう。
例えばAppleの製品は数年利用しても、リセール可能なことが多いです。

引っ越しにあたり、必要最小限の家電は身長しましたが、家具は必要最低限かつ、一人で動かしたり処分しやすいものを選んで購入しました。
08. シングルの視点:将来を見据えた資産管理
40代シングル女性として、親との同居生活を送りながら、自身の将来も見据えた資産管理が重要です。節約だけでなく、長期的な視点での資産形成を考えることが、安定した生活の基盤となります。
シングルの場合、自身の将来に対する経済的準備がより重要になります。同居生活での節約を通じて得た余裕資金を、計画的に資産形成に回すことを考えましょう。
シングルの資産管理のポイント
- 緊急資金の確保: 最低でも3〜6ヶ月分の生活費を貯蓄しておきましょう。
- 年金対策: 国民年金の納付状況を確認し、必要に応じて個人年金も検討します。
- 投資の検討: リスクを考慮しつつ、長期的な資産形成のための投資を考えます。
- 保険の見直し: 自身と親の状況に合わせた適切な保険に加入しましょう。
- 相続対策: 親の資産状況を把握し、将来の相続について話し合っておきます。
同居生活での資産管理の留意点
- 費用分担の明確化: 親との生活費の分担を明確にし、自身の貯蓄計画に組み込みます。
- 将来の介護費用の想定: 親の介護が必要になった場合の費用を予め考慮しておきます。
- キャリアプランの継続: 同居しながらも、自身のキャリア発展を止めないことが重要です。

同居を始めてから、自分の将来設計を見直す良い機会となりました。
親との生活費分担を明確にし、その上で自身の老後資金の積立を始めました。これにより、経済面での不安が大きく軽減されました。
まとめ:持続可能な同居生活のために
高齢の親との同居生活で効果的に生活費を節約するには、以下のポイントが重要です:
- 電気・ガス会社の見直し: 家族の生活パターンに合わせた最適なプランを選択。
- 格安スマホへの切り替え: 必要な機能に絞ったプランで通信費を大幅削減。
- 格安Wifiの活用: インターネット料金を抑えつつ、快適な通信環境を維持。
- 食費の工夫: ネットでの購入や計画的な調理で無駄を省く。
- 医療費の適切な管理: 健康保険の最適化と医療費控除の活用。
- 趣味や娯楽の共有: 家族で楽しめる節約アクティビティの導入。
- シングルの視点での資産管理: 将来を見据えた計画的な資産形成。
これらの方法を実践することで、家計の負担を軽減しながら、充実した同居生活を送ることができます。重要なのは、家族全員が協力し、お互いの生活スタイルを尊重しながら取り組むことです。
節約は一朝一夕には達成できません。小さな努力の積み重ねが、長期的には大きな成果につながります。また、節約だけでなく、家族の健康と幸福を第一に考えることを忘れないでください。
最後に、同居生活は挑戦でもありますが、家族との絆を深める素晴らしい機会でもあります。経済面での工夫を通じて、より豊かで満足度の高い生活を築いていけることを願っています。
親との同居生活を始めて1年が経ちました。確かに課題もありますが、家族と過ごす時間の大切さを日々実感しています。この記事で紹介した方法は、私自身が試行錯誤を重ねて見出したものです。皆さんの状況に合わせてアレンジし、より良い同居生活のヒントにしていただければ幸いです。
この記事が、同じような状況にある方々の参考になれば嬉しいです。同居生活には様々な形があり、一つの正解はありません。家族との対話を大切にしながら、あなたらしい同居スタイルを見つけてください。